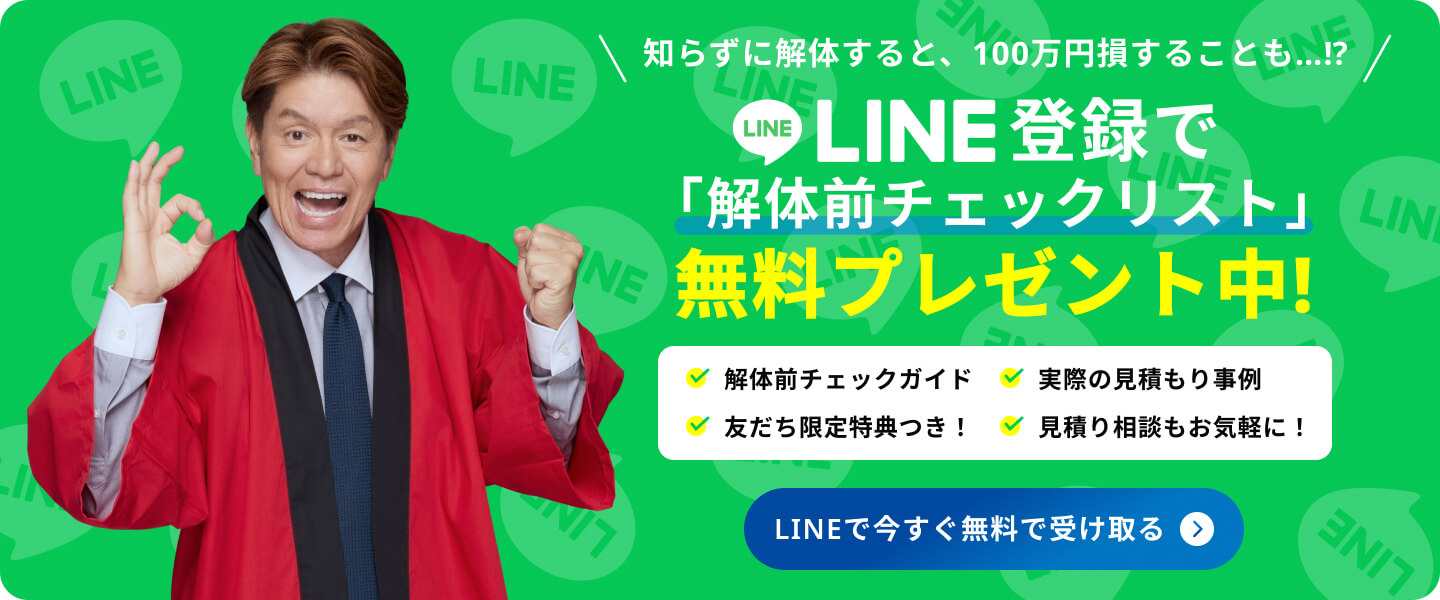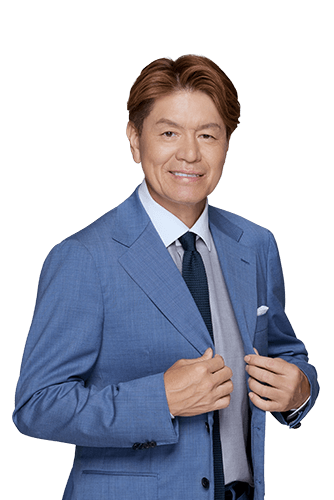ブロック塀の高さ制限のルールご存知ですか?
広島・東広島・三原・尾道・福山のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「うちのブロック塀って、もしかして高さ制限に引っかかってる?」「古くなってきたし、倒れたりしないか不安……」そんなお悩みはありませんか?実は、ブロック塀には安全のための高さ制限が法律で定められており、オーバーしている場合には解体や補強が必要になるケースもあります。
この記事では、ブロック塀の高さ制限の具体的な基準から、違反した場合のリスク、解体にかかる費用や補助金制度まで丁寧に解説しています。この記事を読むことで、ブロック塀に関する疑問が解消され、安全で安心な住まいづくりに一歩近づけますよ。古いブロック塀が気になる方や、解体を検討中の方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
解体のことなら、
どんな些細なことでもご相談ください
アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。

0120-084-085
24時間365日お電話対応!
0120-084-085
24時間365日お電話対応!
ブロック塀の高さ制限とは?建築基準法に基づくルールを解説
ブロック塀の高さ制限とは、地震や倒壊事故を防ぐために建築基準法で定められた上限の高さのことです。これは安全性を確保するための法律上のルールであり、違反していると危険性が高まるだけでなく、違法建築物とみなされる可能性もあります。
具体的な制限内容(建築基準法による)
建築基準法施行令第62条の8により、以下のように定められています。
- ブロック塀の高さは最大2.2メートルまで
- 高さが1.2メートルを超える場合は「控え壁(補強壁)」の設置が必須
- 控え壁の間隔は3.4メートル以内
- 壁の厚みや鉄筋の配置にも細かい規定あり(例えば、厚さはブロック長さの1/10以上 など)
なぜ高さ制限が必要なのか?
2018年の大阪北部地震では、高さ制限を超えたブロック塀が倒壊し、小学生が犠牲になるという事故が発生しました。この事故を受けて、全国的にブロック塀の安全性の見直しが進み、各自治体でも点検や是正指導が強化されています。
ブロック塀の高さ制限オーバーが危険な理由とは?
建築基準法の高さ制限(最大2.2m)を超えたブロック塀は、構造上の安定性が著しく低くなるため、倒壊のリスクが一気に高まります。次にその具体的な理由を紹介します。

1.地震で倒壊する可能性が高い
ブロック塀は地震の横揺れに弱い構造です。
特に、高さがあると「てこの原理」で上部に力が集中しやすく、揺れによって根元から折れるように倒れてしまうケースがあります。
- 例:2018年の大阪北部地震では、高さ制限を超えたブロック塀が倒壊し、登校中の児童が巻き込まれて死亡するという事故が発生しました。
2.老朽化で崩れやすくなる
高さだけでなく、築年数が古く、鉄筋の入っていないブロック塀も非常に危険です。
中には40年以上前に施工されたまま手つかずというケースも少なくありません。
- 時間とともにモルタルが劣化し、接着力が弱まり、わずかな力でも崩れる状態になることがあります。
3.通行人や隣家に被害を与えるリスクがある
ブロック塀は、住宅の境界や道路沿い、学校周辺など、人の通行が多い場所に設置されていることが多く、倒壊すると大きな事故につながります。
- 倒れた塀が歩行者や車両に直撃すれば、命に関わる事故や重大な損害賠償問題にもなりかねません。
4.災害時に避難経路をふさいでしまう可能性も
地震や大雨などの災害時にブロック塀が倒れると、避難経路をふさいでしまうリスクもあります。
これは、火災や土砂災害の避難を妨げ、さらなる被害を生む原因になります。
安全のためにできること
- 高さを確認し、1.2m以上なら控え壁の有無をチェック
- ひび割れ、傾き、グラつきがある場合はすぐに専門業者へ相談
- 解体や補強工事を早めに検討する
高さ制限を超えたブロック塀は解体が必要?その判断ポイント
結論から言うと、高さ制限(原則2.2m以下)を超えたブロック塀は、原則として「解体または補強」が必要です。特に、老朽化している場合や安全基準を満たしていない場合は、早めの解体が推奨されます。

判断のポイントはここ!
1. 高さが2.2mを超えている
建築基準法違反となり、行政指導や改善命令の対象になる可能性があります。
2. 控え壁が設置されていない
高さ1.2mを超えているにもかかわらず「控え壁(補強壁)」が無い場合は、倒壊リスクが高い状態です。
3. ヒビ・傾き・ぐらつきがある
高さ制限を超えていなくても、構造の劣化や強度不足が見られれば、解体が望ましいです。
4. 鉄筋が入っていない・腐食している
昔のブロック塀には鉄筋が入っていないケースが多く、見た目以上に危険です。鉄筋が腐食している場合も同様です。
補強と比較して、解体が適しているケースとは?
一部のブロック塀は「控え壁の設置」や「フェンスへの交換」で補強が可能な場合もありますが、次のような場合は補強ではなく、解体の方が安全で合理的です。
- 築30年以上が経過している
- 全体的に劣化やヒビ割れが進行している
- 道路や学校などに面していて人通りが多い場所
- 過去に地震や台風で揺れた際に異音や傾きが生じたことがある
解体のメリット
- 安全性が飛躍的に向上する
- 行政からの指導や苦情対応を回避できる
- 地震や風災に備えた家全体のリスク軽減
- 解体後に軽量なフェンスや生垣に切り替えることでメンテナンスもラクに
ブロック塀の解体費用はいくら?相場と内訳を解説
ブロック塀の解体費用は、一般的に1平方メートルあたり5,000円から10,000円程度とされています。
例えば、高さ1.2メートル、長さ10メートルのブロック塀(面積12平方メートル)を解体する場合、約60,000円から120,000円の費用が見込まれます。
この費用には以下の項目が含まれます。
- 人件費:作業員1人あたりの費用
- 運送費:重機やトラックの現場持ち込み、廃材の運搬費用
- 廃材処分費:解体したブロックの処分費用。
なお、解体方法やブロック塀の量、種類、地域によって費用は変動します。重機が使用できる場合は費用が抑えられる一方、手作業での解体が必要な場合は人件費が増加します。
補助金制度の活用
多くの自治体では、地震などによるブロック塀の倒壊を防ぐため、撤去費用の一部を補助する制度を設けています。補助金額や条件は自治体によって異なりますが、一般的には工事費用の1/2から2/3、上限20万円から40万円程度が支給されるケースが多いです。
補助金活用のポイント
- 事前申請が必須
補助金の申請は、解体工事前に行う必要があります。
工事後の申請は受け付けられない場合が多いため、注意が必要です。 - 自治体ごとの条件を確認
補助対象となるブロック塀の条件や補助金額は自治体によって異なります。
お住まいの自治体の公式ウェブサイトや窓口で詳細を確認しましょう。 - 申請手続きのサポート
解体業者の中には、補助金申請の手続きをサポートしてくれるところもあります。業者選びの際に確認すると良いでしょう。
解体時の注意点と業者選びのポイント
ブロック塀を安全に解体するためには、事前準備と信頼できる業者選びが重要です。
近隣への配慮と事前説明
解体工事には騒音や振動が伴うため、近隣住民への事前説明やあいさつ回りが欠かせません。
信頼できる業者であれば、近隣対応のサポートも万全に行ってくれます。
業者選びのチェックポイント
適正価格で安全に作業を行うためには、実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。
具体的には、「建設業許可の有無」「補助金申請のサポートをしてくれるか」などを確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
A:必ずしも即解体というわけではありません。
ただし、違反状態が続いていると行政から是正指導を受ける可能性があります。
また、老朽化や傾きがある場合は倒壊のリスクが高いため、早急な対応が望まれます。
補強工事で対応できるケースもありますが、安全面・長期的コストを考慮して、解体を選ばれる方が多いです。
A:必須ではありません。しかし、多くのケースでは隣地との境界線を明示するために何らかの構造物を設置します。軽量フェンス・生垣・アルミ支柱など、選択肢は多数あります。将来的なメンテナンスや見た目のバランスも考慮して、ライフスタイルに合った囲い方を選ぶとよいでしょう。
まとめ|広島の解体工事はACTIVEにお任せ!
ブロック塀の高さ制限を守ることは、法律のためだけでなく、大切な人の命を守るためにも非常に重要です。見た目には問題なくても、老朽化や高さ制限オーバーのブロック塀は倒壊のリスクが高まります。この記事で紹介したように、費用の目安や補助金制度を活用すれば、負担を抑えて安全な環境を整えることが可能です。身近なブロック塀を今一度見直してみましょう。広島・東広島・三原・尾道・福山で解体工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
ACTIVE(アクティブ)では、広島・福山エリアでお客様にピッタリの解体工事を提案しています。広島市・東広島市・三原市・尾道市・福山市で、解体工事・アスベスト調査はACTIVE(アクティブ)にお任せください!!
アスベスト調査については、こちらのページで詳細をご覧ください。
建物解体のことでお困りごとはありませんか?
アクティブは圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。