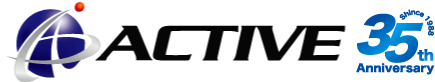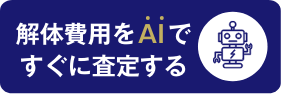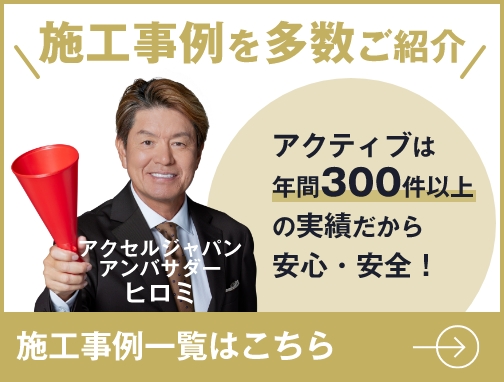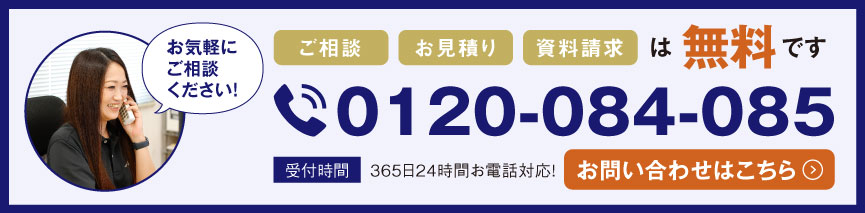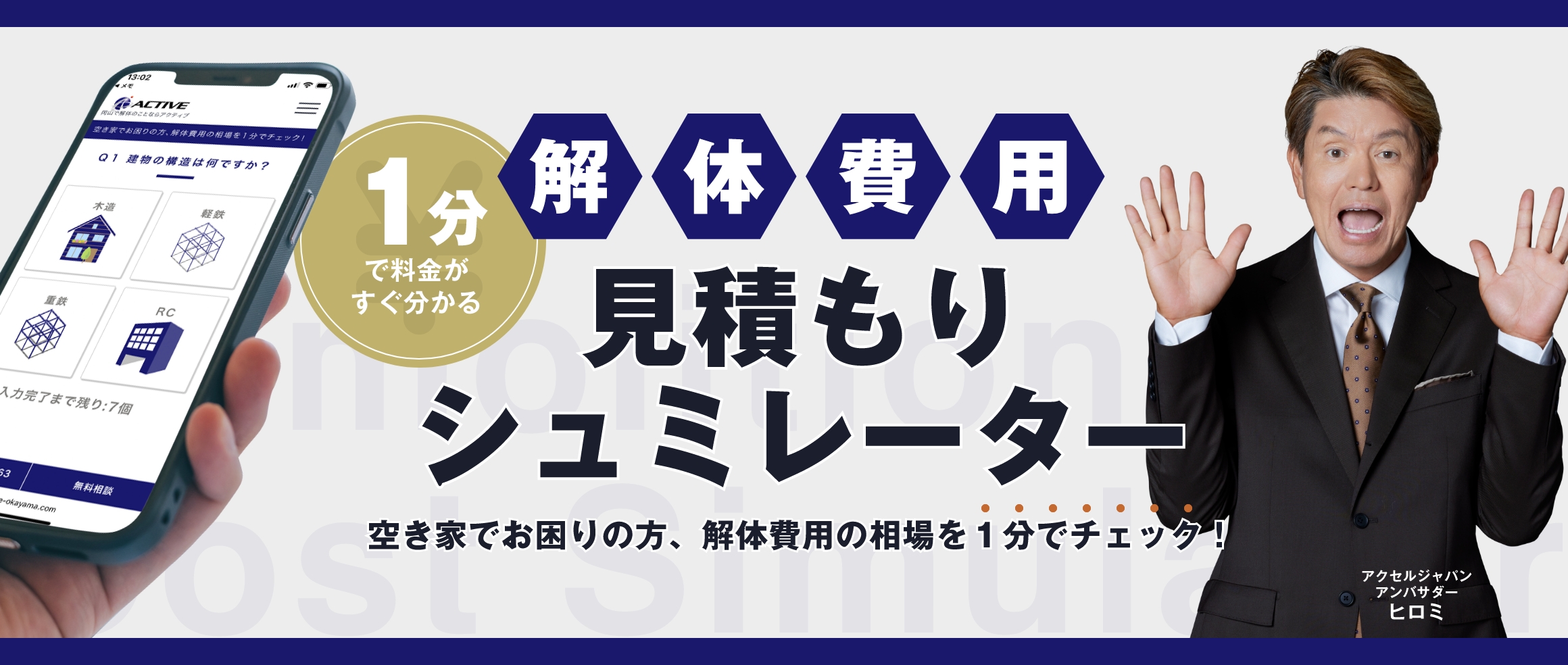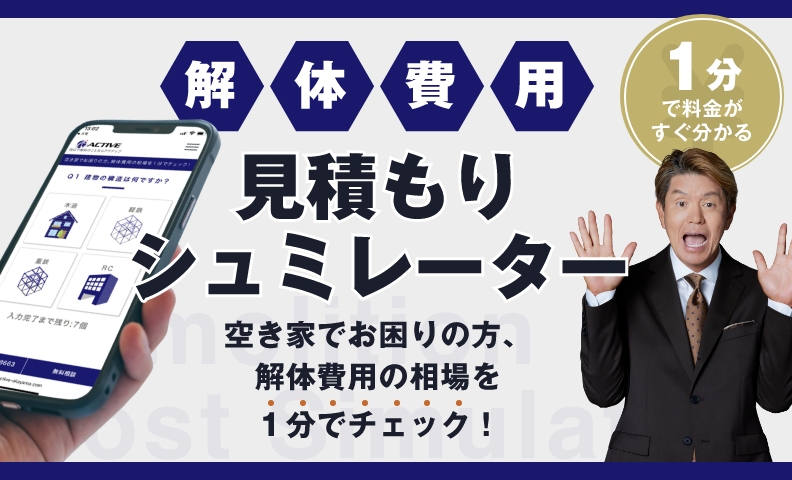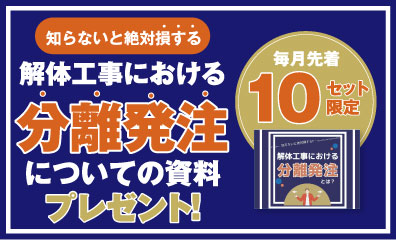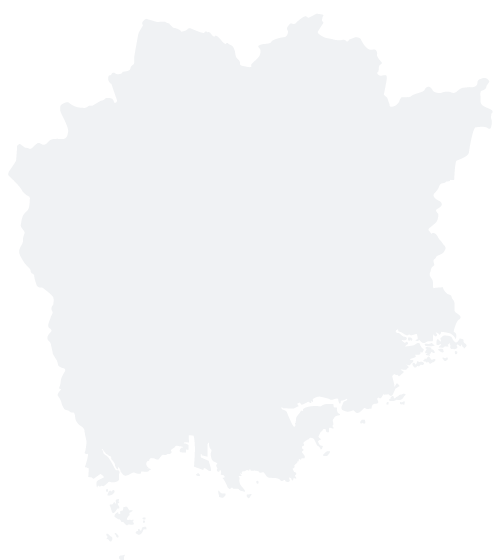古いブロック塀は、地震が起きたときに人や物に損傷を与える恐れがあります。不安定なブロック塀やひびが多く入っているものは、解体を検討することをおすすめします。
しかし、ブロック塀は建築基準法で高さが決められていたり、法律で境界線のルールが決められていたりと、さまざまな規定があります。古いからといってすぐに取り壊すのではなく、境界線や塀の所有者を確認してから工事を進めることが大切です。
この記事では、ブロック塀の危険性や解体時に考えられるトラブルについて説明しています。ブロック塀の解体を検討している方は、参考にしてみてください。
解体のことなら、どんな些細なことでもご相談ください
アクティブは岡山で
圧倒的な実績と経験を誇る地域No.1の解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。
ブロック塀の倒壊は思わぬトラブルになる可能性がある
ブロック塀は倒壊するとかなりの衝撃があるため、人や物に大きな損傷を与える恐れがあります。またブロック塀の倒壊によって事故を起こした場合は、損害賠償を請求される可能性もあります。
ここでは、ブロック塀の危険性や倒壊したときの危険性を確認しましょう。
ブロック塀の危険性
ブロック塀が不安定だった場合、地震などが起きると塀が人や物の上に倒れる危険性があります。古いブロック塀のなかには耐震基準に満たしていないものもあります。傾きやヒビがわかったら、早めに修理をすることが望ましいでしょう。
ブロック塀は見た目だけでは「古い」「新しい」を判断できないこともあります。見た目に不自然な点がなくても「築後20年以上建っている」など明らかに古い場合は、工事を検討しましょう。
ブロック塀の構造
ブロック塀は、中が空洞になっているブロックを積み上げて作られるのが一般的です。建築基準法施行令では、ブロック塀がすぐに倒れないための条件として「高さ2.2m以下」と定められています。高さ1.6m、長さ1mのブロック塀の場合は320〜400Kgほどの重さがあり、倒れたらかなりの衝撃があることがわかります。
地震や雨、風や日射から家を守ると同時に、音や犯罪から守るのもブロック塀の役割です。
ブロック塀が倒壊した際の責任
地震などによってブロック塀が人に怪我をさせたり物を壊したりした場合、ブロック塀の所有者が責任を問われ、損害賠償に応じなければなりません。過去には6,000万円を超えた損害請求を起こされた例もあります。
不安定なブロック塀を放置することは危険なうえ、大きな損害賠償に応じなければならない可能性があることを理解しましょう。
危険なブロック塀の特徴
ここでは、危険なブロック塀の特徴を解説します。これらの問題点が見つかった場合は、ブロック塀の工事を検討しましょう。
目で見て明らかに傾いている
目で見て明らかに傾いているブロック塀は、大きな台風や地震によって倒れる恐れがあります。すぐに解体工事が必要といえるでしょう。土台から不安定なブロック塀や、手で押してぐらつくようなブロック塀は特に危険なため、工事を急ぐようにしましょう。
ひび割れが見られる・ボロボロになっている
長年雨風にさらされると、ブロック塀にひび割れが入ったり、ボロボロになっていたりします。ひびを放置するとひびから雨水が入って中を通る鉄筋を錆させ、ブロック塀をもろくしてしまう可能性があります。
小さなひびは簡単に補修できる場合もありますが、ひびが大きい場合は工事を検討しましょう。

基準よりも高さがある
ブロック塀は、建築基準法で高さが決められています。
ブロック塀の高さは、地盤から2.2m以下が基本です。これより高い場合は倒壊の恐れもあるため危険です。塀の高さが2.2m以下になっていない場合は、工事を行うことをおすすめします。
耐震補強がされていない
耐震補強がされていないブロック塀は、地震で倒壊する恐れがあります。建築基準法に定められた基準を守っているか確認しましょう。ブロック塀の厚さや土台があるかなど、基準を満たせていない場合は工事をしましょう。
石垣の上に建っている
石垣の上に立っているブロック塀は、安定性に欠けるため危険です。ブロック塀の下の石垣に揺れに対応する対策がされていなければ、地震が起きたときに崩れる恐れがあります。
ブロック塀を安定させるためには、コンクリートの基礎が必要です。自分で見てわからない場合は、専門家に確認してもらうようにしてください。
ブロック塀の解体でトラブルを避けるために注意すべきポイント
「ブロック塀が傾いている」「耐震補強がされていない」といった場合は、ブロック塀を1度解体する必要があります。ここでは、ブロック塀解体時にトラブルを避けるために注意すべきポイントを説明します。
登記上の境界線を把握しておく
隣家とのトラブルを避けるために、登記上の境界線を把握しておきましょう。
土地の境界線には、「所有境界」と「筆界」があります。「所有境界」は塀などに囲まれた部分の土地、「筆界」は土地が登記された際に定められた線です。「所有境界」と「筆界」は本来一致しているべきですが、建て替えなどを経て違いが発生している可能性があります。
建物と隣地境界線に関する法律を把握しておく
建物と隣地境界線については、法律で「境界から50㎝以上の距離を保たなければならない」と定められています。この基準を満たしていない場合、隣地の所有者はブロック塀の工事を中止・変更させることが可能です。
一方で、地域によっては「50cm以上離す必要はない」と考えられているところもあります。解体する前に、隣家と話し合っておくと安心です。
ブロック塀の解体や新設に関する法律を把握しておく
ブロック塀の解体や新設については、それぞれ決まったルールがあります。ここでは、それぞれの場合において知っておくべきルールを説明します。
境界線上に新設する場合
隣接地との間に空き地がある場合、他の所有者と話し合いのうえ費用を分担して、境界にブロック塀などを設置することが可能です。
もし話し合いがまとまらない場合は、板塀や竹垣などの材料で高さが2m以内の物であれば設置できます。その場合、費用は所有者が負担します。
自分の敷地内に新設する場合
自分の敷地内にブロック塀を新設する場合、特に規定はなく自由に設置できます。
ただし、もし設置したブロック塀が倒れて隣家に損害を与えてしまった場合は賠償しなければなりません。自分の敷地内に設置する場合であっても、ブロック塀の取り壊しを行う旨、隣家に声をかけておくのが安心です。
今ある塀を解体してから新しい塀を設置する場合
今ある塀を解体する場合、既存の塀の持ち主が誰かによって対応が異なります。
自分が所有者である場合、自分で費用を負担すれば取り壊しは自由にできます。念の為隣家に声をかけておくと安心です。
既存の塀を共有している場合は、隣家の同意を確認して費用を折半するのが基本です。ただし、相手が費用負担を嫌がる場合は、相手の費用負担割合を少なくしたり、負担なしにしたりすることも可能です。

ブロック塀の解体トラブルを防ぐための配慮
ブロック塀の解体は、隣家に配慮しなければトラブルの元になってしまいます。ここでは、解体トラブルを防ぐためのポイントを説明します。
近所挨拶をしっかり行なっておく
ブロック塀を解体する際は、近所に挨拶して解体工事が入る旨を説明しておきましょう。工事は騒音が発生しやすいため、声をかけておくと近所からのクレーム予防につながります。
解体業者が入る場合は、業者から近所に工事の内容などを説明してもらうとさらに安心です。
解体前にブロック塀の所有者を確認しておく
ブロック塀を解体する前に、所有者を確認しましょう。
ブロック塀の所有者が自分であれば、隣家の許可は不要で自分の費用だけで進めることになります。しかし隣家と所有権を共有していた場合は、隣家と話し合って費用は折半するのが基本です。
隣家と所有権を共有しているものの、もし相手から費用負担の同意を得られなかった場合は、自分が全額負担することになります。
なるべく複数業者に相見積もりを取る
ブロック塀の解体を業者に依頼する場合は、できるだけ複数業者に相見積もりを取りましょう。複数の業者に依頼することで、適切な費用かを判断できます。
また、業者の態度などが原因で近隣の方とトラブルになる可能性もゼロではありません。業者の口コミや評価を確認し、近隣への対応も含めて心配がないか確認するとよいでしょう。
まとめ
古いブロック塀は、地震が起きたときに事故の元となります。不安定なブロック塀やひびが多く入っているものは、解体を検討したほうがよいでしょう。
ブロック塀は建築基準法で高さが決められていたり、法律で境界線のルールが決められていたりします。古いからといってすぐに取り壊すのではなく、境界線や塀の所有者を確認してから工事を検討するようにしてください。